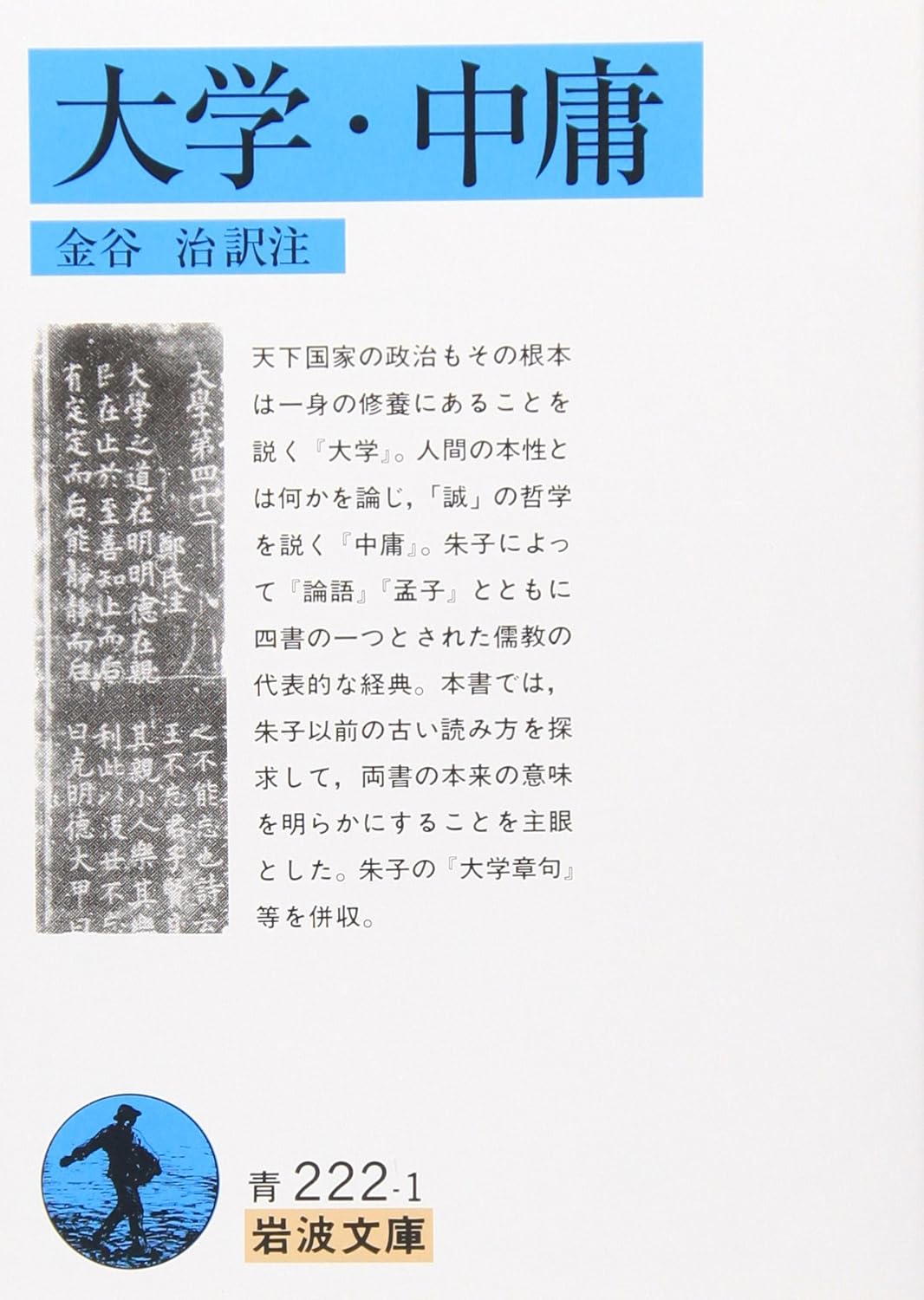「大学・中庸」(朱子 著、金谷治 訳注・岩波書店 刊)を題材に、ビジネスを強化する儒教の哲学「大学」について解説していきます。文章中の一部の語句にwikipediaへのリンクを設置していますので、興味のある方は合わせてご覧ください。
儒教とは古代中国の教説で「己れ自身を修める」道徳説と「人を治める」民衆統治の政治説を兼ねた「修己治人」の哲学・思想から成り立っています。儒教の経典である「四書」を(1)大学(2)論語(3)孟子(4)中庸の順に学べば、人は誤りを犯すことがないとされています。今回は「四書」の中から「大学」を題材に、ビジネスを強化・発展させるために経営者が持つべき価値観について解説していきます。
「大学」は元々は古代中国の哲学者、曾子(そうし)が孔子の教えを基にして著したものを、後に朱子(朱熹)が四書としてまとめたとされる「理(自然界の秩序)を極め、心を正し、わが身を修め、人を治める」ための方法を説いた経典です。
その中で特に重要なキーワードとして「三綱領(さんこうりょう)」という言葉が登場します。そのポイントは3つあります。
三綱領
- 明明徳(天命を明らかにする)
- 親民(民を親しめる)
- 止至善(善に止まる)
人には必ず自然界の秩序の上で割り当てられた役割すなわち「天命」があり、まずは自らの天命を悟ることから善く生きることは始まるとしています。
また「大学」では、天下の本は国家にあり、国家の本は家庭にあり、家庭の本は自らにあると説いています。国家をよく治めるには、必ずまずその家庭を和合(円満に)する必要があり、そのためには自らを律することが重要だとしています。その価値観をまとめたものは「八条目」と呼ばれています。
八条目
- 格物(道理を極める)
- 致知(知を極める)
- 誠意(誠意に生きる)
- 正心(心を正す)
- 脩身(身を修める)
- 斉家(家を整える)
- 治国(国を治める)
- 平天下(天下を平らかにする)
天下を治める1〜8の順に物事を実行していくことが説かれています。「大学」の要諦でもあるこの「八条目」は、現代における経営やマネジメントに求められる価値観とも一致しており「八条目」を理解することは、ビジネスパーソン(特に経営層、管理職、マネジメント職)の方にとって非常に重要です。
また「大学」にはビジネスにおける決断を支える重要な価値観が多く示されています。下記にいくつか紹介していきます。
「大学」に学ぶ経営力を強化する価値観
- 君子(上司)に求められるのは「仁(人を思いやること)」
- 臣下(部下)に求められるのは「敬(慎み欺かないこと)」
- 子供に求められるのは「孝(親を敬い仕えること)」
- 親に求められるのは「慈(子の幸福を願い与えること)」
- 人との交友で求められるのは「信(友情に厚く誠実なこと)」
- 道義を守ることこそ本当の利益
- 怒り、恐れ、好楽、憂患(心配事)があるときは正しい判断ができない
- 君主としてすぐれた人物を重用できないのは怠慢
- 君主として善くない人物との関係を絶ちきることができないのは過失
- 民を治めるには赤子を慈しみ育てるようにする
- 好きな相手でも同時にその欠点をわきまえ、嫌いな相手でも同時にその長所をわきまえる
- 「徳」から「人(人間)」「土(土地・国土)」「財(財産・経済)」「用(活用・目的)」の順に発展する(誠実でなければ社会は発展しない)
- 「徳」は本なり、「財」は末なり(誠実でなければ財産は集まらない)
- 財産が集まるときは民が散じ、財産を散じるときは民が集まる(財物を民間に流すことで民心が得られる)
- 物を作ることが能率的で、消費するほうが緩慢であれば国の財物はいつも豊か
- 国を豊かにする方法は「本(根本)」を務めて「用(働き)」を節することにある(倫理観を備え倹約すれば豊かになる)
- 厳しく重税をとりたてる家臣を置いてはならない
- 理を窮め、心を正し、わが身を修め、人を治めるための方法を教える「大学」に対して、小学校では基本となる六芸(掃除・人とのうけこたえ・立ち居ふるまい・礼儀作法と音楽・弓射や馬車の扱い・読み書きと算数)を教えた
このように、儒教においては「徳」を非常に重視しますが「徳」とは「誠実」であることを意味します。「徳」を備えた経営者はその人望から経営に貢献する人々が周りに集まり、物事がうまく運ぶ(運が良い)ため事業を成長させることができます。経営者が手本としたい「徳」を備えた人格者を儒教では「聖人君子」と呼びます。次に聖人君子とはどのような人を意味するのかを示していきます。
聖人君子とは
- 「三綱領」「八条目」(前述)を体現している
- 身近な一定の規準から広い世界を推し測る「絜矩(けっく)の道」を知る
- 聡明と叡智を備えて十分に本性を発揮する
- 民の父母として人を思いやる広い心がありそれが外見に現れる
- 先聖を祭る(先の聖人、先祖に恥ずべきことがない)
さて、ここまで見てきたように「大学」は、「徳」を重んじることで人間社会に太平をもたらすことを説いた思想であると言えます。
それではこのような思想は何を根拠にして成り立ったのでしょうか。これを知るためには自然界を支配する法則(摂理)にヒントがあります。最後にこれを示してまとめとしたいと思います。
自然の法則(摂理)
- 自然のめぐりは循環して、極点まで至ったものは必ずもとに復る
- 性は善なり(善を好んで悪を憎むのが人の本性)
- 人間は生まれながらに四徳(仁・義・礼・智)を与えられている
- 万物は理と気によって成りたっている(理は最高善だが気に蔽われ情欲があらわれて善悪がまじりあうことになる)
- 悪事を好むのであれば必ず災難が身にやって来る
- 物に本末あり、事に終始あり(物事の根本と末端、始まりと終わりには因果関係がある)
「徳」の重要性を認識していても聖人君子のような生き方ができる人は少ないと思いますが、歴史上には聖人君子と呼ばれるような偉大な政治家や経営者が実在してきたことも事実です。「大学」の価値観は、ビジネスパーソン(特に経営層、管理職、マネジメント職)の方が新たな事業に挑戦する際や難しい問題にぶつかった際に、目的地までの道案内をしてくれるのではないでしょうか。
このような本質的で内容の濃い情報が詰まった本書「大学・中庸」(朱子 著、金谷治 訳注・岩波書店 刊)を是非お手に取っていただくことをおすすめします。なお、本書には「大学」だけでなく「中庸」という経典も含まれています。「中庸」については「ビジネスを強化する儒教の哲学『中庸』について」で紹介していきます。
書籍の詳細は下記の表紙画像をクリックしてご覧ください。
(当記事執筆者:辻中 玲)